「スマホメモ 仕事と人生の質を上げるすごいメモ術」 著:須藤 亮 マーケティングプランナー
〇本を読んで得られる価値
メモを仕事や日常生活の中で活用している人は多くいるだろう。以前に比べれば紙に手書きでメモするよりスマホのメモアプリを使用する人もかなり増えてもいるのではないか。メモの有効性は多くの人が認めるところであるし、異論はない。そのうえでより「メモをする」という行動の価値を高める方法論を提案してくれるのが本書だ。
内容
概要
筆者はある時ふとしたアイディアをスマホにメモをする。※以下スマホメモという
これが後にスマホメモに大きな可能性を感じ、実践し続けることでこの方法に価値を見出した。
そもそもメモとは何か。メモを日本語でいうならば備忘録。
余談だが、備忘録 忘れる事に備える、こういう日本語は好き。単語を構成する漢字一つ一つがうまく全体を表している。味わい深い。
人間の脳はすぐに忘れる、ふとした考えや、ちょっとした気づきなど、それは誰しもが経験があるだろう。それを書きとめておくのがすなわちメモである。
ポイント①
筆者が考えるスマホメモの利点として自分の思考の整理がある。
思考が整理されることの私の疑似体験として人と話しているうたに自分の思考が整理され、新しい発見や、自分の意見がより体系化されたことがある。似たような経験をしたことがある人も多いのではないだろうか。
人と話すことで腑に落ちる感覚といってもいい。
この自分の考えが俯瞰し、洗練されていくのをスマホメモそすることで得られるのだ。
人との繋がりが減った今この手法が今の自分に合う可能性はあると感じた。
ポイント②
著者はスマホメモをインプットとアウトプットの間の作業と位置付けている
良質な情報に触れたからといって良質な発信ができているか?(インプットとアウトプット)それができている人はおそらくそう多くはないだろう。すくなくとも私は現段階ではできていない。
筆者はインプットしたものを消化する行為をスマホメモとし、インプットしたものに対して自分がどう感じたかや、何に気付いたのか、何を学んだのか。それらを自らの言葉で記すことでより良質なアウトプットとできることを説明してくれている。
この情報を消化することに時間を割くようになり、新聞を読む量など以前よりインプット量が減ったそうだ。
デメリットのような気もするが、これは筆者からの問題提起だあるといえる。
多くの著名人やインフルエンサーはインプットの重要性を発信し続けているし、その考えに異論はない。
現に自分自身はインプット量の少なさを実感しこの本を手にとった。ただ現状社会には情報が溢れ、消化する前に次の情報が入ってくるというのが現実ではないか。
次から次に入ってくる情報に対して処理が追いつかないと思考停止をしてしまう。
読んで気付いた点
今まで私はインプットとアウトプットは対義語として理解していたが、そうではなくインプットしたことをアウトプットまでしないと価値が低くなってしまうという気付きが本書から得られた。
例えば、工場で新人がやり方を教えられても見て理解しただけでは生産性が低く、実際に作業を担当してもらわないと実益につながらないみたいなこと。
暗黙知と形式知の話に似ているともいえる。熟練の職人が感覚的にやっていることを言語化してマニュアル化することで新人でも生産性の高い作業ができる。自分が瞬間的なフワッとしたアイディアがメモにすることで感覚的なものから具体的な言葉へ置換されて第三者に発信できる情報として整理される。
感想
スマホが当たり前になった現代社会でメモの新しいスタイル提案としての面白さがある。
メモをテーマにした書籍は他にも多数あることから需要がありそう。
インプットとアウトプットの間にメモの役割を位置づける考えは参考になった。
具体的な取り組み方が気になった人は是非読んでもらいたい。
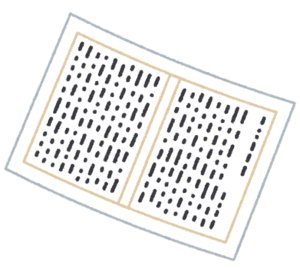
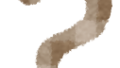
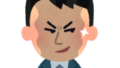
コメント